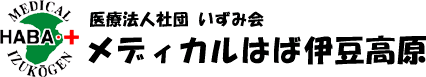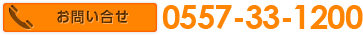「暗黙知」無意識が支える社会の営み
2025.02.12
昨年10月11日付け日本経済新聞紙面の半歩遅れの読書術欄に俳人の黛まどかさんが、興味の惹かれる内容を載せていらっしゃったので全文を紹介させていただきます。
長嶋茂雄氏はヒットのコツを「ビュッと来たらバッと打つ」と答えたという逸話がある。『暗黙知の次元』(マイケル・ポランニー著、高橋勇夫訳、ちくま学芸文庫)を読むと、スポーツは「暗黙知」の上にあると思う。”成す”のではなく”成る”のだ。形式知がデータや数値、言葉など客観的に表示されるものであるのに対し、「暗黙知」は経験の中で獲得する個人に根ざした技能や知識だ。
私たちは言葉にできるより遥かに多くのことを知っていると言う。例えば人は100万人の中からでも家族の顔を識別できる。しかしどのように見分けているかはわからない。
「個々の運動からそれらの共同目的の達成に向かって注意を払う」。それゆえピアニストは自分の指の細部の動きに注意を集中させると、演奏が止まってしまうらしい。暗黙知とは、個別の諸要素から、包括的な全体像を知覚することだ。
歩く、食べる、会社に通う・・・・日々の営みは暗黙知に支えられ、同時にその営みが暗黙知を作り続けている。
暗黙知は無意識下で身体が習得するため、詳細に表現することも、他者に伝達することも不可能だ。畢竟(ひっきょう)「身体が知っている」のだ。したがって生きた身体を持たない人工知能(AI)には暗黙知は習得できない。
仏教では「不立文字」(ふりゅうもんじ)という。悟りは自らの体験を通して身体で感得してゆくもので、文字や言説で表出することはできず、伝達も共有もできない。まさに暗黙知だ。
ポランニーは一つの例を挙げる。洞窟内を探り棒を使って歩く時、初めは指や掌に衝撃を感じるが、やがて棒の先端が対象に触れていく感覚へと変化する。ただの衝撃=「無意味な感覚」が、地面の形状という「有意味な感覚」に換えられてゆく。棒が指の延長線上になるのだ。以前、宮大工の小川三夫さんに、道具は手の延長線上の存在かと尋ねると、「そうだな」と即答した。
社会は暗黙知に満ちている。というより、情報や科学等の形式知に乏しかった時代、先人たちが暗黙知によって積み上げた社会を礎に、今を生きているのだ。現代はデータ、生産性、AIなど「形式知」が優位な社会だ。それは「見える化」という意味では有意義だが、その背後にある膨大な暗黙知を軽視してはならない。また、一人一人が暗黙知を積み上げながら生きている。だからこそ人は掛け替えがないのだ。
リハビリテーション室 吉和田 裕資